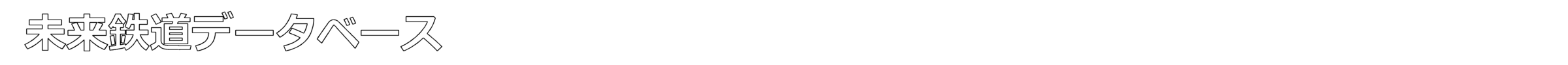新白線は、国鉄赤谷線を延伸して国鉄磐越西線に接続し、新潟県の新発田市と三川村白崎(現在の阿賀町白崎)を短絡することが考えられていた鉄道の構想。
ルート

ルートは決まっていなかった。赤谷線の赤谷駅で分岐して磐越西線の白崎駅(現在の三川駅)に向かうことが考えられており、おおむね現在の新潟県道14号新発田津川線に沿うルートになっていたとみられる。
経緯
新発田と赤谷鉱山を結ぶ鉱石運搬用の農商務省専用線が1922年までに整備された。このころ、周辺自治体が新潟~新発田を結ぶ両新鉄道(現在の白新線)の整備に加え、専用線の国鉄線化と磐越西線の白崎駅への延伸を国に要望した。1925年に専用線が国鉄赤谷線として開業。1941年には赤谷~東赤谷が延伸開業している。
戦後も白崎駅への延伸を求める運動が続き、鉄道公団が発足してまもない1964年5月には、赤谷線と磐越西線の沿線自治体(当時の新発田市・津川町・鹿瀬町・三川村)を母体とする新白線建設促進期成同盟会が発足している。
しかし1968年には、国鉄諮問委員会が赤谷線を含む国鉄ローカル線の廃止を提言した。このときは存続したものの、1980年には国鉄再建法の公布で国鉄ローカル線の整理が本格的に行われることになり、翌1981年に赤谷線が第1次特定地方交通線に指定。1984年に廃止された。
新白線も改正鉄道敷設法の予定線や鉄道公団の基本計画に組み入れられないまま、建設運動が終了している。
データ
区間:赤谷~白崎
距離:約20km