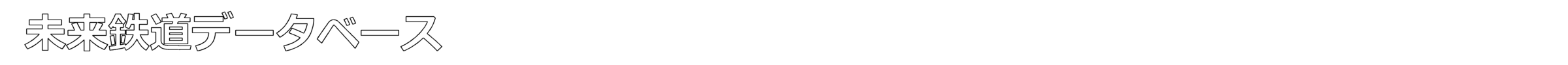阪急宝塚線のバイパス線は、阪急電鉄が計画していた新線。神戸本線(神戸線)と宝塚本線(宝塚線)の複々線化と「神崎川・曽根線」(「曽根新線」とも呼ばれる)の整備を組み合わせ、大阪~宝塚の輸送力増強を図ることが考えられていた。
ルート

神崎川・曽根線は、神戸線の神崎川駅で分岐して北上し、宝塚線の曽根駅に合流する。あわせて神戸線の十三~神崎川と宝塚線の曽根~豊中を複々線化し、実質的には宝塚線・十三~豊中の急行線とする計画だった。
経緯
阪急電鉄は1948年に神崎川・曽根線の軌道特許を取得。1951年には工事施行認可も申請した。しかし1960年代に入ると、阪急電鉄は現在の千里線と箕面線を連絡する千里山延長線(千里山~桜井)を整備して宝塚線の混雑緩和を図る方針に転換。神崎川・曽根線と神戸線・宝塚線の複々線化は事実上中止された。
千里山延長線は1961年12月に地方鉄道免許を取得して1963年8月に千里山~南千里が開業。しかし、その後は大阪府の要望を受けて北千里への延伸に変更された。また、このころには宝塚線の輸送力増強が進んだことや北大阪急行電鉄の開業もあり、1972年12月に南千里~桜井の地方鉄道免許を廃止した。
1970年代には神崎川・曽根線を取り込む形となる空港線(西梅田~十三~伊丹空港~北伊丹)の構想が浮上したこともあり、神崎川・曽根線の軌道特許は引き続き維持された。しかし阪急電鉄が持株会社制に移行する直前の2005年2月に工事施行認可の申請を取り下げ、軌道特許が失効した。
データ
事業者:阪急電鉄
線名:神崎川・曽根線
区間:神崎川~曽根
距離:4.0km
種別:軌道事業
種類:軌道
軌間:1435mm
手続き
1948年4月19日:軌道特許(京阪神急行電鉄)
1951年4月3日:工事施行認可申請
1973年4月1日:名称変更(京阪神急行電鉄→阪急電鉄)
2005年2月23日:工事施行認可申請の取り下げにより特許失効