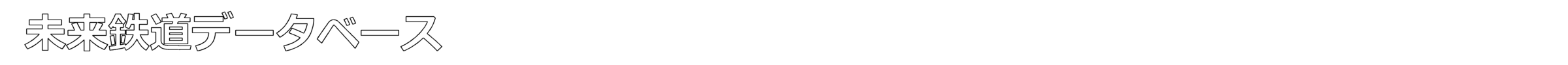新大阪連絡線は、阪急各線と新大阪駅を結び、新幹線への連絡を図ることが考えられていた阪急電鉄の計画。一部の区間を除き中止された。
ルート

新大阪連絡線は淡路~新大阪~十三と新大阪~神崎川の2区間で構成され、先に軌道特許を受けていた神崎川・曽根線も含め阪急線の京都・宝塚・神戸の各方面から新大阪駅へ直通できるようにすることが考えられた。淡路~新大阪~十三は京都本線(京都線)の急行線としても使用する計画だった。
新大阪駅は新幹線の同駅ホーム北側に並行して島式ホーム2面4線の構造で整備する計画だった。東海道新幹線や山陽新幹線、東海道本線、大阪市営地下鉄(現在の大阪メトロ)御堂筋線は新大阪連絡線との立体交差に対応した構造で建設されている。
経緯
戦前に東京~下関を結ぶ高速鉄道(弾丸列車)が計画された際、現在の阪急電鉄の神戸本線(阪急神戸線)と京都本線(阪急京都線)を弾丸列車の新大阪駅(現在の東海道本線・淀川駅北側)経由で結ぶ鉄道が計画され、1941年に地方鉄道免許を申請した。しかし弾丸列車の計画中止で、この申請も実現しなかった。
戦後に東京~新大阪を結ぶ東海道新幹線が計画されると、京阪神急行電鉄(現在の阪急電鉄に相当)が改めて新大阪連絡線の地方鉄道免許を申請し、1961年に免許を取得した。しかしルート上の用地買収の難航などから計画は進まず、事実上の凍結状態になった。
淡路駅を高架化する連続立体交差事業が本格的に動き出した2003年、阪急電鉄は他路線の輸送力増強などにより整備の意義が薄れたなどとして、淡路~新大阪と新大阪~神崎川の第1種鉄道事業を廃止した。その一方、新大阪~十三は新大阪駅周辺の開発状況を見ながら今後の方針を決定するとして計画を存続。現在はなにわ筋連絡線と一体的に整備することが考えられている。
データ
事業者:阪急電鉄
線名:新大阪連絡線
区間・駅(1):淡路~新大阪~十三
距離(1):4.03km
区間・駅(2):新大阪~神崎川
距離(2):2.963km
種別:第1種鉄道事業
種類:普通鉄道
軌間:1435mm
動力:電気(直流1500V)
単複:複線
手続き
1961年12月26日:地方鉄道免許(京阪神急行電鉄)
1973年4月1日:名称変更(京阪神急行電鉄→阪急電鉄)
1987年4月1日:※みなし第1種鉄道事業免許
2000年3月1日:※みなし第1種鉄道事業許可
2003年3月1日:第1種鉄道事業廃止(淡路~新大阪・新大阪~神崎川)