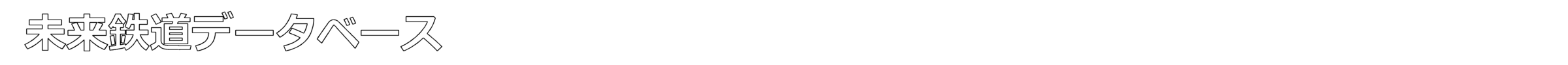川崎縦貫高速鉄道線は川崎市が計画した鉄道新線。川崎市内を内陸部から湾岸部まで横断する路線を市営地下鉄として整備することが考えられていた。「川崎市営地下鉄」「川崎縦貫鉄道」などとも呼ばれる。
概要
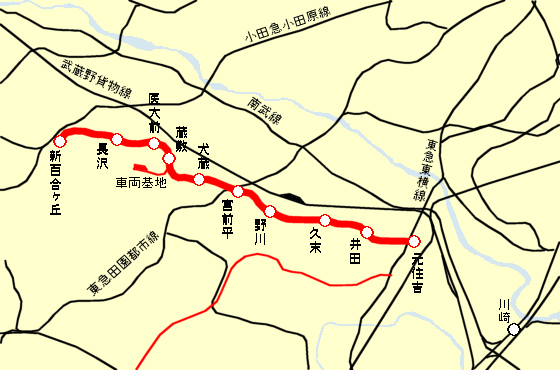
1966年7月15日に都市交通審議会が策定した答申第9号において、大師河原~百合ヶ丘の地下鉄整備が盛り込まれた。1985年7月11日策定の運輸政策審議会答申第7号では、これに代わって武蔵野線の貨物バイパス線(武蔵野南線)の旅客線化と武蔵野南線から新百合ヶ丘へ伸びる分岐線の整備が盛り込まれた。
1990年代に入ると再び地下鉄建設構想が浮上。新百合ヶ丘~宮前平~元住吉~新川崎~川崎間に地下鉄を建設し、連続立体交差事業により地下化される京急大師線に接続して相互直通運転を図る方針が固まった。当初は事業主体を第三セクターとすることが考えられていたが、のちに市営地下鉄として建設、運営する方針に変わっている。
川崎市は2001年5月、初期整備区間として新百合ヶ丘~元住吉の第1種鉄道事業許可を取得した。この時点の計画では、4両編成の列車を1日163往復運行。野川駅(見直し案では宮前平駅)に待避施設を設け、急行運転を実施するものとしていた。設計最高速度は90km/hとし、新百合ヶ丘~元住吉の所要時間は急行列車が約18分、普通列車が約26分としていた。
しかし、財政難や採算性の問題から川崎市は計画の再検討を実施。初期整備区間の開業時点では小田急多摩線の唐木田車両基地を利用することで車両基地の建設費を削減することにした。このため軌間を京急線の1435mmから小田急線の1067mmに変更し、相互直通先も京急大師線から小田急多摩線に変更した。全線整備時に実施する京急大師線との直通は、軌間可変電車(フリーゲージトレイン)の導入や改軌を視野に入れた。
こうして2003年4月に見直し案をまとめたが、市民アンケートで着工延期を求める声が多かったこと、市の財政状況の問題などから、同年6月には着工を5年程度延期する方針を表明した。
2005年2月には、初期整備区間の久末以東のルートを変更し、等々力緑地を経由して武蔵小杉駅を終点とすることで採算性の確保を図るルート変更案を川崎市が発表。さらに国土交通省も初期整備区間の事業を中止するとした事業再評価結果を同年8月に公表したことから、川崎市は翌9月に初期整備区間の鉄道事業廃止を届け出た。
その後は蓄電地電車や燃料電池電車など新技術の導入も含めて検討が進められたが、採算性などの問題をクリアにすることはできず、2015年度に計画を休止。2017年度限りで計画の廃止が正式に決まった。
データ
※第1種鉄道事業許可時
事業者:川崎市交通局
線名:川崎縦貫高速鉄道線
区間・駅:新百合ヶ丘~長沢~医大前~蔵敷~犬蔵~宮前平~野川~久末~井田~元住吉
距離:15.4km
種別:第1種鉄道事業
種類:普通鉄道
軌間:1435mm
動力:電気(直流1500V)
単複:複線
手続き
※第1種鉄道事業の手続きのみ
2001年5月11日:第1種鉄道事業許可
2005年9月9日:第1種鉄道事業廃止届出
2005年11月4日:第1種鉄道事業廃止繰上届出
2006年4月1日:第1種鉄道事業廃止