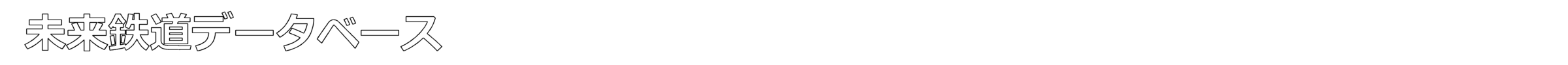中央新幹線は、東京都から甲府市付近、名古屋市付近、奈良市付近を経て大阪市に至る新幹線鉄道の建設線。東京~大阪の新幹線の二重化によるリダンダンシーの確保を図る。
「リニア中央新幹線」「中央リニア新幹線」などとも呼ばれ、最高速度500km/hレベルの超電導磁気浮上式のリニアモーターカーで整備する。現在は東京都内の品川駅から名古屋駅までの区間が工事中。
ルート

太平洋沿岸の都市を結ぶ東海道新幹線に対し、リニア中央新幹線は直線に近いルートで東京~名古屋を結ぶ。赤石山脈(南アルプス)などの険しい山岳地帯を長大トンネルで貫き、東京と名古屋の大都市圏も大深度地下トンネルで整備する。全体の86%がトンネルで、地上に出る部分は40km弱しかない。
建設区間のうち山梨県内の一部はリニアモーターカーの山梨実験線を転用する。この実験線は、都留市朝日曽雌~大月市笹子町笹子の18.4kmが1996年までに先行区間として完成し、翌1997年から実験開始。2013年には上野原市秋山から笛吹市境川町まで42.8kmの全体区間が完成した。
駅は品川駅・神奈川県駅・山梨県駅・長野県駅・岐阜県駅・名古屋駅を設ける。起点の品川駅は、JRの東海道新幹線や東海道本線、山手線などが乗り入れる東京都港区内の既設同名駅に併設。東海道新幹線ホームの直下に地下駅を建設する。
神奈川県駅は、JRの横浜線と相模線が合流する相模原市内の橋本駅近くに整備。同駅の南側に地下駅を建設する。山梨県駅は甲府市大津町に高架駅を整備。JRの在来線から大きく離れた独立駅になる。
神奈川県駅から長野県駅のあいだでは静岡県北部の山岳地帯をトンネルで通るが、駅は設けられない。
長野県駅は、JR飯田線との交差地点(伊那上郷~元善光寺)の東側に高架駅を建設する。飯田線にも新駅を整備して乗り換えできるようにする構想があったが中止された。岐阜県駅は、中津川市内にあるJR中央本線の美乃坂本駅近くに整備。同駅の北側に高架駅を建設する。
名古屋駅はJRの既設同名駅に併設。東海道新幹線や東海道本線に交差するようにして地下駅を建設する。
運行計画
運行計画は未定。品川~名古屋の所要時間は東海道新幹線「のぞみ」で約1時間半。リニア中央新幹線は40分で結び、現在の「のぞみ」より50分ほど短縮される。
事業方式
JR東海が建設し、完成後もJR東海が運営する。事業費は2023年12月時点で7兆482億4000万円(車両費を含む)。2014年10月時点では5兆5235億5000万円とされ、そこから1兆5000億円ほど膨張している。
開業時期
現行計画上は2027年以降の開業を予定しているが、大幅に遅れる可能性が高い。
2014年10月の工事実施計画認可時点では、2027年の開業を予定していた。しかし、静岡県が中央新幹線の建設による大井川の流量減少を懸念して県内区間の着工を認めなかったことに加え、沿線の岐阜県瑞浪市で井戸水の水位が低下するなど工事の難航が各地で続出。工事スケジュールは大幅に遅延している。
このためJR東海は2023年、計画上の開業予定時期を「2027年以降」に変更した。実際は2034年以降の開業になるともいわれている。
データ
◆基本計画決定(1973年11月15日)
◆整備計画決定(2011年5月23日)
◆工事実施計画認可(2014年10月17日)
営業主体:東海旅客鉄道
建設主体:東海旅客鉄道
線名:中央新幹線
区間・駅:品川駅~神奈川県駅~山梨県駅~長野県駅~岐阜県駅~名古屋駅
距離:285.6km
種類:超電導磁気浮上式鉄道
動力:電気(交流3万3000V)
軌間:-
単複:複線
開業予定時期:2027年以降 ※大幅に遅れる見込み